わたし実は高校3年生の18歳の時から今(25歳)まで7年と半年ずーっとおなじ人と付き合ってるんですね。
今まで本当に全く喧嘩とかなくて、まあ今回の結婚の件も喧嘩とは思ってないんですが(実際空気悪くなったりとかは一切してないので)、いろいろ結婚式とか結婚指輪について話し合ってる最中なので何か参考になればと思って垂れ流しておきます^^笑
【プロポーズ】夢破れるもみえり

わたし結構プロポーズとか結婚式とかにキラキラした夢を見てきた人間なんです。ディズニープリンセスとかテレビドラマとかでの刷り込みも大きいかなとは思うのですが、10年以上かけてつくりあげてきたキラキラした夢はわたしにとって大きなものになっていました。
ただ、わたしのプロポーズの実際は全くキラキラしてないものでした…
〜熱海に旅行に行ったある日〜
私たちカップルは旅行が好きで、国内外問わず1年に1~2回くらい旅行に行ってます。
熱海に泊まったのは2泊3日か3泊4日かそのくらいだったと思うのですが、地元の魚を使ったお寿司を食べたり、なんか有名らしいイタリアン食べに行ったり、イケメンのお兄ちゃんがいるバーに遊びに行ったり、たまたまやってた花火みたりいろいろ楽しかったです。
街中を散歩してた時に見つけた「熱海山口美術館」っていうところにも寄りました。その時お客さんがわたしたちふたりだけで、ルノワール、ピカソ、岡本太郎、草間彌生、奈良美智などの作品をめちゃくちゃ近くでゆっくり見たり触ったりすることができてすごい面白かったのはいい思い出。
帰り際マグカップの絵付け体験もしました!

さあここからが本題です。泊まった旅館で結婚についての話し合いをしました。
もみえり「結婚さ、どう思ってるの?」
彼「どう思ってるっていうか、別にするメリットが特にないというか。逆になんでしたいの?」
もみえり「若くてぴちぴちの時に結婚式挙げたいし、ばあちゃんじいちゃんももう長くないし…確かに今の時点で制度的に夫婦になってもならなくてもあんまり変わんないけど、逆にだったら今でもいいんじゃない?って思ってる」
彼「うーん。まあ、じゃあいいよ。」
という煮え切らない感じで、結婚することが決まりました(笑)
話し合いは今までも何度かあったものの、具体的にスケジュールが決まったのはこの熱海旅行が初めてでした。
もっとなんかこう、キラキラした素敵なプロポーズがいいからやり直してって言ってるんですが、彼にその気はないようです…確かに別に男だからプロポーズしなきゃいけないわけじゃないし、プロポーズに対する熱量はわたしの方が確実に高いから、なんかわくわくサプライズ〜的なのやろうかな〜…笑
【結婚式・結婚指輪】揺れる天秤〜人生においてどれくらい重要かって話〜
こんな感じで、彼は結婚に対しての熱量が0.1ミリ立方センチメートルくらいしかない人なので、そりゃあ結婚式も結婚指輪も興味ナシ、お金も別にかけたくないというスタンス。
それに対してわたしは「ガーデンウェディングがいいな〜」とか「かわいいドレスが着たいな〜」とか「海外でフォトウェディングもしたいな〜」とか「指輪は旅行先とかで見つけた思い出が詰まったようなのがいいな〜」とか、まあいろんな理想があるわけで。
自分の人生でどれくらい「結婚」を重要視しているかという個人の問題だから、お互いにどこまで歩み寄れるかの話になってくるわけです。

今も話し合い続行中なので結果は呼ばれた人のお楽しみって感じなんですが、今のところこんな感じです。
- 挙式だけ結婚式場でやってレストランウェディングをするか式場で披露宴までやるか
- ガーデンウェディングをするか全部屋内でやるか
- 結婚指輪を買うか買わないか、買うのであればどこで買うのか(ネックレス案もある)
それに加えてコロナ禍で先の見通しがつかないのもあるので、最終的に2021年内に決めようという長期戦です。
結婚式ってそもそも何?

ここからは結婚式の日本の歴史を見ていき、結婚ってどんな意味があるのかちょっと考えてみたいと思います。というのも、自分がいざ結婚をするということになって、「そもそも結婚式ってなんじゃい」という疑問が浮かんだので「ルーツを調べてみよう!」となったわけです。小難しい話はカンベンっていう人は読み飛ばしてください!
日本の古代は性におおらかな時代で、飛鳥時代・奈良時代になって唐の律令の影響で日本の結婚にもある程度ルールができました。平安時代になると、源氏物語にも出てくる通い婚での婿入り婚(男性が女性の家族の一員になる)になり、鎌倉時代・室町時代に武士の時代がやってくると嫁入り婚(女性が男性の家族の一員になる)になります。この時、数日間かけて儀式を行いますが、皆にお披露目するような式というよりは、夫婦になるためのしきたりを行なっている感じ。
安土桃山時代になると、儀式が豪華になっていき今でも行われている「三三九度」や「お色直し」が始まります。江戸時代は仲人が仲を取り持つようになったり三三九度を婿が先にやるようになったりとやり方が変わっていきました。江戸時代には庶民の間でも嫁入りと祝言(婚礼)が行われていたそうです。
明治に入るとのちの大正天皇が神前式の形式で結婚式を行い、「結婚式」というものに対しての国民の関心が強まりました。
昭和初期にはメイク衣装写真が全部できる総合結婚式場が誕生していましたが、戦後、焼け野原になった関東で今までのように自宅で結婚式ができなくなった人々は公民館などで式をあげていました。
やがてホテルや総合結婚式場での結婚式が普及していき、その後高度経済成長期、バブル期とどんどん結婚式が派手になっていきます(ゴンドラとかおっきいケーキとか)。
そして結婚式は儀式というより結婚式場がカップルに提供する全国画一化された商品になったわけですね(今は「こだわりの結婚式」「オリジナル結婚式」とかあるけど結局それもパッケージ化された商品であることに変わりはない)
※ここに書いたのは平安までは公家の世界の話だし鎌倉以降は武士の世界の話で史料に残ってない庶民の結婚がどうだったかとかはわからないし、もちろん地域差があっただろうことは想像に難くないです。
ここから読み取れることとしては、時代や身分によって結婚の儀礼のやり方が変わっていて、庶民は家同士の婚礼として各家庭で行われていたものが、戦後だんだんとイベント化・商品化されていっているということです。
(参考:結婚指輪の専門店SANJI「結婚式はいつから始まった?」)
(参考:高松 百香「中世の結婚と離婚 : 史実と狂言の世界」)
(参考:太田市社会教育関係認可団体マルチメディア推進協議会「冠婚百科」)
(参考:三澤武彦写真事務所「新・日本の結婚式の歴史」)
わたしたちの結婚式の意味をもう一度考えてみる

確かに、わざわざ結婚式という儀式なのかエンタメイベントなのか人にとって捉え方の変わるお金のかかることをしなくても役所に届ければ結婚はできます。
じゃあなんでわたしと彼はわざわざ結婚式なんてやるんでしょうか。
これは式を挙げる人が何を求めているのか、大事にしているのかで変わってきます。だから、あえて何も調べずにあくまでわたしの意見だけ言うと…
- ウェディングドレスとかかわいいカラードレスとか着て結婚式っていう一生に一度しかないイベントを楽しみたい(それが結婚式場に作られ刷り込まれたイメージだとしても別にいい)
- 両親、祖父母が結婚式を楽しみにしてくれている。わたしも晴れ姿を見せてあげたい
- 母と一緒にウェルカムボードを描いて久しぶりに共同作業がしたい
- 彼との結婚式という素敵な思い出を記録に残したい
わたしの意見だけだと不平等なので彼にも結婚式に対してネガティブな理由を改めて聞きました。
- ビジネスモデル上客単価が高いビジネスに乗っかるのが納得いかない
- 呼ぶ友達が少なすぎる
- コストに見合わない
- 別の投資先がある
- 根本的に関心がない
わたしと彼の意見をまとめるとこんな感じ
もみえり
イベントをつくって思い出つくって楽しみたい。親族に向けて自分の大事な節目を見せたい。
彼
とにかくコスパ悪い(結婚式が提供するものに価値を感じてないから)。
まあそもそも結婚式という商品に価値を感じている人と感じていない人が共同で同じ商品を買おうとしているから意見の相違があるのは当たり前です。
わたし自身は「結婚式」って資本主義の台頭からさも正義のようになっているお金での価値の測り方だけであーだこーだ言えるものではないと思ってるし、だからこそ彼が嫌なら別にお金をそんなにかける必要もないとは思ってます。
でも自分が後悔しないような素敵な結婚式にしたいっていう感情はどうしても譲れないから、そこの折り合いをつけていく作業を丁寧にやらなきゃいけないなっていう感じですね。
お互いが歩み寄るために
ここまでお互いの主張を整理できたらこっちのもんで、「わたしが納得できる内容×彼が妥協できる価格=わたし達の求める結婚式」という式の解を最大化させられるようにしていけばいいだけ。
今は結婚式も多様化してて会費制とかで低価格のものもあるし
わたしも彼もおじいちゃんおばあちゃんの身体が心配だから、もし来年式場までくるのが難しいってなったら衣装借りて自宅で写真をとって思い出にするっていう内容の充実のさせ方もあるし
持ち込みOKの式場にしてウェディングドレスにこだわれたらわたしも嬉しいし価格も抑えられるし
いろんなサービスを賢く使いながらお互いが納得して楽しめる式にしたいな٩( ‘ω’ )و
がんばろうぃ٩( ‘ω’ )و
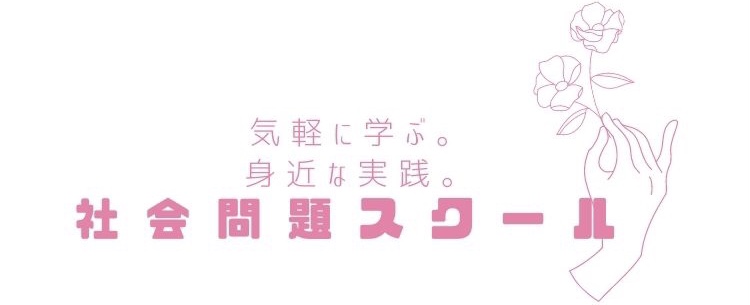



コメント
lan ciddi ciddi çalisiyorr ??
istanbul escort
sakarya escort
türbanlı escort
muğla escort
şirinevler escort
taksim escort
fethiye escort
bodrum escort
halkalı escort
marmaris escort
esenyurt escort
aydın escort
Canlı casino siteleri ile sende en iyi casino sitelerini burada bulabilirsin.
eve otele gelen bayan escort için tıkla
Mükemmel Şartlar <a href="https://foxnews.onelink.me/xLDS?af_dp=foxnewsaf://
Empower Your Blog’s Growth with Our Innovative Advertising Agency Are you ready to elevate your blog to Akseki Escort new heights and attract a larger audience? Look no further than our innovative advertising agency, dedicated to helping bloggers like you achieve remarkable success.
This race to solve blockchain puzzles can require an intense amount of computer power and electricity.
Hi there, its nice article about media print, we all be aware of media is a great source of data.
What i don’t realize is if truth be told how you are now not actually a lot more smartly-liked than you may be now. You’re so intelligent. You know thus significantly on the subject of this subject, produced me personally believe it from numerous numerous angles. Its like men and women are not involved until it is something to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs nice. All the time take care of it up!
izmir escort bayanlar ile sende hemen elit izmir escort bayanlara ulaş.